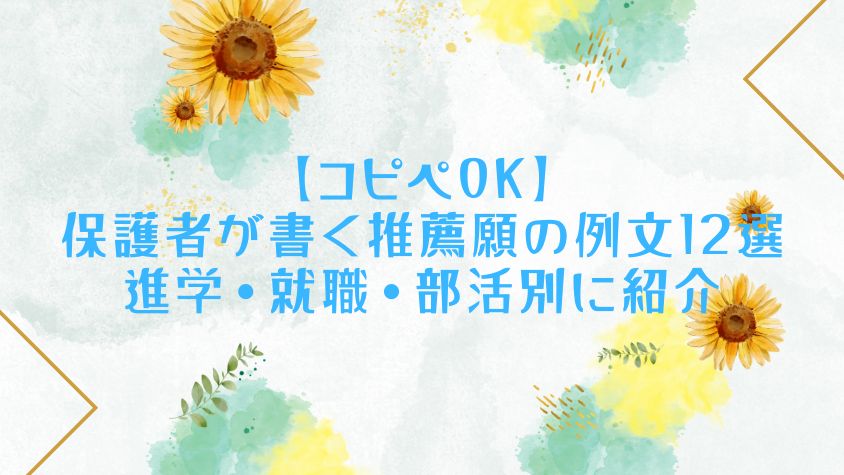
推薦願とは、子どもの進学や就職、部活動への参加にあたり、信頼できる人物であることを第三者として証明・推薦する文書です。保護者が記載する推薦願は、家庭から見たお子さんの人柄や努力を伝える重要な書類であり、進路の選定や選考に大きく影響します。
学校や企業は、単なる学力や成績だけではなく、家庭での様子や人間性も重視することが多く、保護者による推薦願が加点要素になることもあります。推薦願の有無や内容が、合否や採用の可否に直結するケースもあるため、誠意ある推薦が非常に重要となります。
推薦願における保護者の立場と責任
保護者として推薦願を書く際は、あくまで客観的かつ誠実な内容であることが求められます。過度な誇張は避け、実際に目にしてきたお子さんの行動や努力を具体的に記述することが信頼を得るポイントです。
また、推薦することの責任を伴う文書であることを意識し、お子さんの意向や進路の目的にきちんと沿った内容を心がけましょう。一方的な期待や親の希望ではなく、子どもの個性や特性を活かす内容にすることが大切です。
保護者が書く推薦願の例文12 進学・就職・部活別に紹介
推薦願に必ず盛り込むべき項目とは?
推薦願を書く際に含めるべき基本項目は以下の通りです:
-
推薦先の名称(学校名・企業名など)
-
推薦を受ける子どもの氏名と続柄
-
推薦する理由(学習態度・人柄・志望動機など)
-
推薦者である保護者の氏名と連絡先
これらを簡潔かつ具体的に記載することで、読み手の理解と信頼を得ることができます。また、なぜその推薦先を選んだのかという背景を記すと、より説得力のある内容になります。
保護者が注意すべき表現やマナー
推薦願は、形式的な文書であるため、礼儀正しい表現が求められます。例えば「〜でございます」「拝見いたしました」など、敬語を適切に使用することがマナーです。
また、以下の点にも注意してください:
-
文章は事実に基づき、誠実に書くこと
-
手書きが指定されていない限り、PCで丁寧に作成して印刷することも可
-
誤字脱字のチェックを怠らないこと
-
文末の語尾を統一し、丁寧語で締めること
提出前には第三者の目で確認してもらうのも有効です。読みやすさや文脈の整合性を確認することで、より印象の良い文書に仕上がります。
進学用の推薦願:高校・大学別の例文
高校進学(一般・学科・スーパー推薦)向け例文
例文1:
私の娘〇〇は、これまで学業に対して熱心に取り組んでまいりました。特に数学と英語に興味を持ち、自主的に予習復習を行うなど、日々努力を重ねています。中学校では学級委員も務め、責任感のある行動を心がけてきました。貴校の教育理念に共感し、学びたいという強い意思を持っております。
例文2:
息子〇〇は、ものづくりや理科実験への関心が高く、科学部に所属してさまざまな活動に取り組んできました。積極的な姿勢と探究心を持ち、学校生活でも常に前向きに行動しております。貴校でさらに知識を深めたいと強く希望しております。
例文3:
娘〇〇は、学習面だけでなく人間関係においても非常に円滑な対応ができる性格です。中学校の合唱コンクールでは指揮者を務め、クラスをまとめる役割を果たしました。貴校に進学し、さらなる成長の機会を得られることを願っております。
大学進学(指定校・学部別)向け例文
例文1:
息子〇〇は幼少期より読書が好きで、自らの視野を広げようと多様な知識を吸収してきました。高校生活では文芸部の活動にも力を入れ、学園祭では自作の小説を出展するなど、積極的に表現力を磨いてきました。
例文2:
娘〇〇は、ボランティア活動に積極的に参加し、人の役に立つことに喜びを感じる性格です。将来は医療分野で働きたいという目標があり、貴学の看護学部で専門知識を身につけたいと願っております。
例文3:
息子〇〇は、歴史や文化に興味を持ち、歴史検定にも挑戦するなど熱心に学びを深めてまいりました。国際関係学部での学びを通じて、国際的な視野を持った人材として社会に貢献したいという思いを強くしております。
就職活動向けの推薦願:保護者が書く場合のコツと例文
企業宛にふさわしい推薦文の構成例
例文1:
私の息子〇〇は、学生時代より責任ある行動を心がけ、アルバイト先でも接客や店舗運営において信頼を得てまいりました。人との関わりを大切にし、礼儀を重んじる姿勢は、家庭内でも一貫しております。
例文2:
娘〇〇は、チームでの活動において協調性を重視し、グループプロジェクトでもリーダー役として周囲を支えてきました。周囲との信頼関係を築ける人柄は、企業の中でもきっと活かされると確信しております。
例文3:
息子〇〇は、物事に対して最後まで責任を持って取り組む姿勢があります。部活動と学業を両立しながら目標を達成する力を身につけ、働くことへの意欲も高く持っています。貴社での成長の機会をぜひ与えていただけますと幸いです。
職種別に配慮した文例のポイント
例文1(保育士志望):
娘〇〇は、子どもと接することが好きで、地域ボランティアとして保育施設の支援活動に積極的に参加してまいりました。温かく思いやりのある性格で、周囲との協調性にも優れております。
例文2(介護士志望):
息子〇〇は、お年寄りとのふれあいを通じて福祉の道に進みたいという思いを持つようになりました。思いやりと忍耐力を備えており、人に寄り添う力は介護現場でも必ず活かせると信じております。
例文3(ITエンジニア志望):
息子〇〇は、パソコンやプログラミングに興味を持ち、高校では情報処理部に所属して知識を深めてまいりました。論理的な思考と集中力に長けており、IT業界での活躍を志しております。
部活動や課外活動向けの推薦願:意欲と姿勢を伝える書き方
部活推薦に適したエピソード例
部活動や課外活動への推薦願を書く際は、子どもの努力や継続性、チームに与えた影響を具体的に伝えることが大切です。
たとえば「3年間休まず練習に参加し、後輩への指導も積極的に行っていた」など、日常の行動から評価されるエピソードが効果的です。
さらに、日頃の練習だけでなく、学校行事やボランティア活動との両立、仲間とのコミュニケーションの工夫など、広い視点での貢献や姿勢も伝えることで説得力が増します。
また、公式戦での実績や練習態度、仲間との関わり方など、数字や具体例を交えて記述すると、読み手の印象に残ります。たとえば「地区大会で優勝した経験」や「自主練習を欠かさなかった」といった成果や積極性を盛り込むと良いでしょう。
指導者や学校に響く表現とは?
推薦願においては、形式的な言い回しに加えて、子どもがなぜこの活動を続けてきたかという動機や成長した点を感情的に表現することで、読み手の共感を得やすくなります。
たとえば、「厳しい練習を前向きに取り組み続けたことで、精神的に大きく成長しました」といった表現は、本人の変化や成長を印象づける一文になります。
さらに、「団体競技の中で他者の意見を尊重する姿勢が身についた」「自分よりも後輩を気遣う行動が増えた」といった、人間的な成長や社会性の広がりに触れることで、評価されやすい推薦文となります。
推薦願に保護者の想いをどう反映させるか
意向を自然に伝えるための工夫
推薦願において保護者の意向を強く出しすぎると、本人の意志が薄れてしまうという懸念があります。そこで、「日頃からこの分野に情熱を持ち、機会があればより深く学びたいと話していました」というように、子どもの考えを紹介する形で意向を伝えることがポイントです。
また、「保護者としても、○○の姿勢を支えていきたいと感じております」と締めくくると、自然に保護者の想いが伝わります。文中では主語を「私たち保護者は」ではなく「○○が〜と考えていることに、私たち家族も〜」とすることで、主体が子どもにあることを明示的に伝える効果があります。
こうした工夫を通じて、推薦願が一方的な押しつけではなく、子どもの夢や目標を尊重するスタンスで書かれていることが伝わります。
子どもの意志と保護者の応援のバランス
推薦願はあくまでも子どもが主体であることが大前提です。そのため、保護者の立場としては、「見守る」「支える」「背中を押す」スタンスで書くことが大切です。
たとえば、「○○が自ら進んでこの道を志したことに、私たち家族も大いに感動し、今後も応援し続けたいと考えております」といった表現にすると、子どもの意志を尊重しつつ、保護者の思いも伝えられます。
また、「今後困難にぶつかることがあっても、これまでと同じように前向きに取り組んでいくことと信じています」というように、子どもの主体性と将来への期待をあわせて表現することで、より信頼性の高い推薦願となります。
提出前のチェックリスト:見落としを防ぐポイント

必要書類の確認と書き方の見直し
推薦願の提出にあたっては、必要な書類が揃っているか、記入漏れがないかを必ず確認することが重要です。特に、署名欄や日付欄の記入漏れはよくあるミスなので、提出前に再度チェックしましょう。
加えて、封筒の宛名や郵送方法の指定(例:簡易書留など)についても事前に確認しておくと安心です。事務的なミスは評価以前の問題になってしまうため、細部にまで気を配りましょう。
また、書き方としては、誤字脱字や表現のくどさがないかを読み返して確認し、できれば第三者に目を通してもらうのも効果的です。客観的な視点を取り入れることで、読みやすさや伝わりやすさを高めることができます。
提出期限や宛先の間違いを防ぐ対策

提出期限を過ぎてしまうと、推薦自体が無効になるリスクがあるため、早めにスケジュールを立てて準備することが大切です。カレンダーに記入し、アラーム設定をするなどの工夫でうっかりミスを防ぎましょう。
また、宛名の書き間違いや敬称のミスは印象を悪くするため、学校や団体の正式名称・担当者名を正確に記載するよう注意しましょう。
「様」「先生」などの敬称にも気をつけて、形式的なマナーを守ることで、推薦願の信頼性と丁寧さが伝わる文書になります。さらに、提出方法(郵送・持参・オンライン提出など)の確認と、提出後の受理確認まで行えば、万全な対応といえるでしょう。